「あれ?お寺に鳥居がある?」というモヤモヤから
神社とお寺って、別のものだと思ってた。
でも、ときどき不思議な光景に出会います。
鳥居があるのに仏像がある場所。
神社なのに、仏教のお堂がある。
お寺なのに、神さまの名前が書かれている──

実はこれ、「日本では昔からけっこう普通」だったんです。
実は、神と仏は一緒にいた。
昔の日本では、「神さまと仏さまは別の存在」という考え方はあまりありませんでした。
日本には、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」という独特の信仰文化があり、
神道と仏教が対立することなく、お互いを補い合うようにして共存していたのです。
たとえば平安時代には、「神は仏が人々を救うために姿を変えたもの(=本地垂迹)」という考え方が広まりました。
その結果、神社にお堂が建てられたり、お寺に神さまが祀られたりするのはごく自然なことでした。
ところが――
明治時代になると、国の方針として「神道は神道、仏教は仏教」と分ける動きが強まりました。
これがいわゆる「神仏分離令」と呼ばれる政策です。
このとき、全国各地でお寺と神社が分離され、仏像や仏具を壊された場所もあったといいます。
それ以前の日本人にとっては、「神も仏も、どちらも大事にする」ことがごく自然な感覚でした。
そしてその“柔らかい信仰のかたち”は、制度が変わった今も、どこかに生き続けているのかもしれません。
「お寺なのに鳥居がある」「神社なのに仏さまがいる」──
そんな“ごちゃまぜ”な信仰の名残が、今も各地に残っています。
ここでは、神仏習合の面影を今に伝える、代表的な場所を紹介します。
- 🏯 四天王寺(大阪府大阪市)
-
聖徳太子によって建てられた、日本で最も古いお寺のひとつ。
境内には石でできた鳥居があり、「ここは仏さまが説法する聖なる場所」という意味の文字が掲げられています。
仏教のお寺なのに鳥居がある──まさに、神と仏が自然に共存していた名残が今も感じられる場所です。 - ⛩ 宇佐神宮(大分県宇佐市)
-
全国の八幡さまの総本社として有名な神社。
ここは、日本で初めて**神と仏が一緒に祀られた場所(神仏習合発祥の地)**とも言われています。
今も境内には、神道と仏教が交わった文化の足跡がたくさん残っていて、“混ざる信仰”のルーツに出会える場所なんです。
七福神は“ごちゃまぜ信仰”の代表選手
七福神を見てみると、信仰のミックスぶりがよく分かります。

- 恵比寿:日本神話の神
- 大黒天:インド由来、仏教にも登場
- 弁財天:インドの水の女神サラスヴァティーが起源
- 毘沙門天・布袋・福禄寿・寿老人:中国の道教や仏教にルーツあり
バラバラな出身なのに、仲良く並んでる。
「この神さまは正しい、この神さまは違う」なんて言わない。
そこには、多様性を受け入れる日本人の信仰の姿があります。
- 🐟 恵比寿(えびす)
-
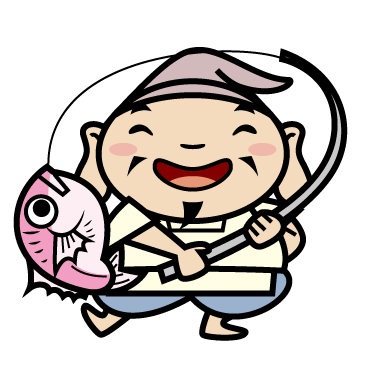
- 起源:日本神話に登場する「蛭子命(ひるこのみこと)」や「事代主神(ことしろぬしのかみ)」と習合
- 元々は「漁業の神」「商売繁盛の神」として民間信仰に広まり、七福神の一柱に
- 唯一の“純日本産”とも言われるが、実際は神話と民間信仰のミックス
- 🍚 大黒天(だいこくてん)
-

- 起源:インド神話の「マハーカーラ(大いなる黒)」=シヴァ神の化身
- 仏教に取り入れられ、護法神として日本に伝来
- 後に日本の「大国主命(おおくにぬしのみこと)」と習合し、五穀豊穣や縁結びの神へと変化
- 🎼 弁財天(べんざいてん)
-
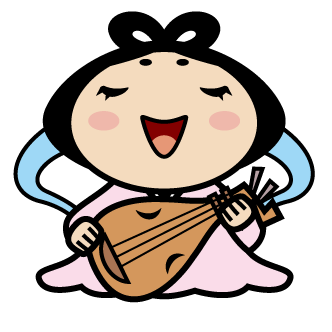
- 起源:インドの水と芸術の女神「サラスヴァティー」
- 仏教に取り入れられ、音楽・学芸・財福の女神として日本へ
- 日本では「弁財天」となり、七福神の中で唯一の女性神
- 🛡 毘沙門天(びしゃもんてん)
-

- 起源:インド神話のクベーラ神(財宝・戦の神)
- 仏教に取り入れられ、「四天王」のひとりとして北方を守護
- 日本では勝負事・武運長久・商売繁盛の神として信仰される
- 😄 布袋尊(ほていそん)
-
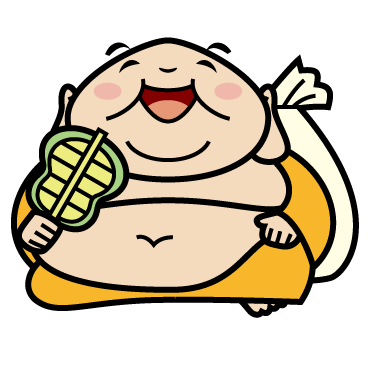
- 起源:実在したとされる中国・唐代末期の禅僧「契此(かいし)」
- 太鼓腹に大きな袋を背負い、子どもたちに慕われた逸話が広まった
- 笑顔と福をもたらす象徴として、「弥勒菩薩の化身」とも言われる
- 🎴 福禄寿(ふくろくじゅ)
-

- 起源:中国・道教における「福=幸福」「禄=財運」「寿=長寿」の三徳を神格化した存在
- 長い頭、巻き髭、杖と経典を持つ姿
- 主に健康長寿・家庭円満のご利益とされる
- 🎋 寿老人(じゅろうじん)
-

起源:中国・道教の「南極老人星」を神格化した長寿の神
鹿(長寿の象徴)を連れ、巻物と杖を持つ姿が特徴
延命長寿・知恵・穏やかさを象徴
外国人から見ると、ちょっと不思議?
海外では、信仰の線引きがもっとはっきりしている地域が多いです。
「キリスト教徒ならこの神を」「ヒンドゥー教ならこの神を」といった具合に、“どの神を信じるか”がアイデンティティに直結していることも珍しくありません。
そんな中で、初詣は神社、法事はお寺、そしてクリスマスも楽しむ日本人のスタイルは、「ゆるすぎる」と思われることもあります。
でも、それは裏を返せば──
形式や教義にとらわれず、心で信じることを大切にしているとも言えるのです。
ガネーシャが人気になる国、それが日本
インドの神さま「ガネーシャ」も、日本で人気を集めている神さまのひとつ。
ゾウの頭を持ち、商売繁盛や学問の神として知られています。
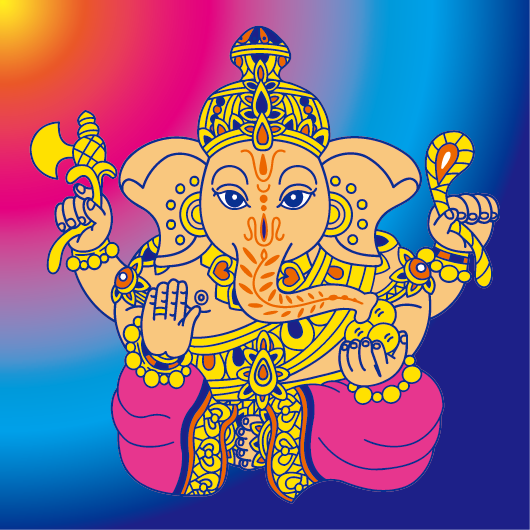
日本では『 夢をかなえるゾウ 』という本で広まり、キャラクターとしても受け入れられているガネーシャ。
本来はヒンドゥー教の神なのに、宗教というより“願いや祈りの象徴”として愛されている姿は、まさに日本的な信仰の柔らかさを象徴しているように感じます。
「信じ方にルールはない」が、開運のヒント
「何を信じたらいいか分からない」
「どれが正しいか分からない」
そんなふうに悩んでしまう人もいるかもしれません。
でも、日本の信仰文化を見ていると、こう語りかけられているように思います。
信じ方にルールなんてない。あなたが大切に思える形で、祈っていいんだよ
開運とは、ラッキーを拾うことじゃなく、“自分の心に正直に生きること”から始まるのかもしれません。
「私はこう信じたい」と決めることで、心に芯が通り、運も流れも整っていく。
そんな優しい在り方が、日本には昔からあったのです。
また来てね。




